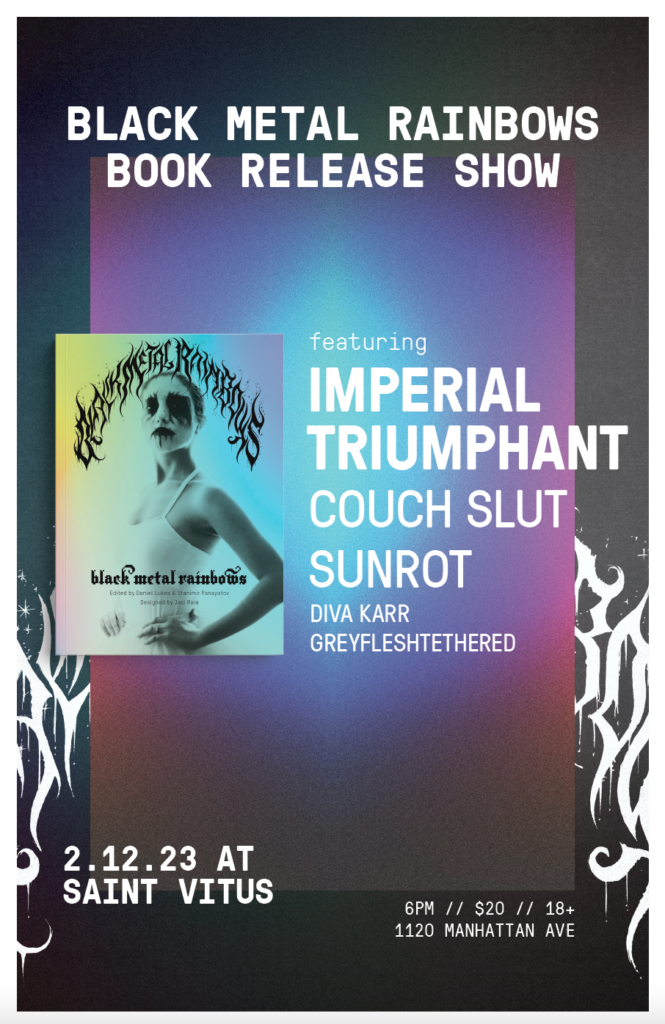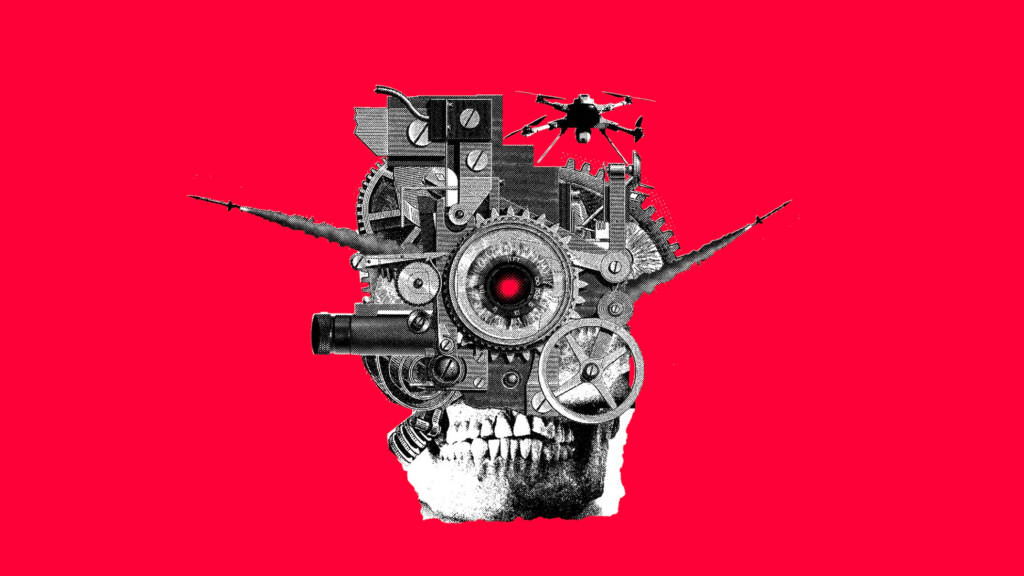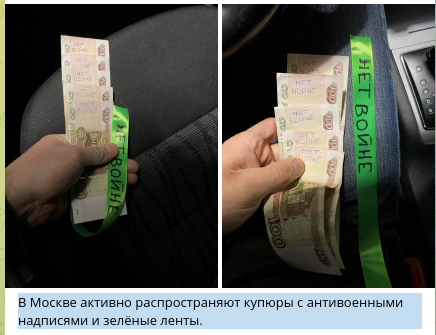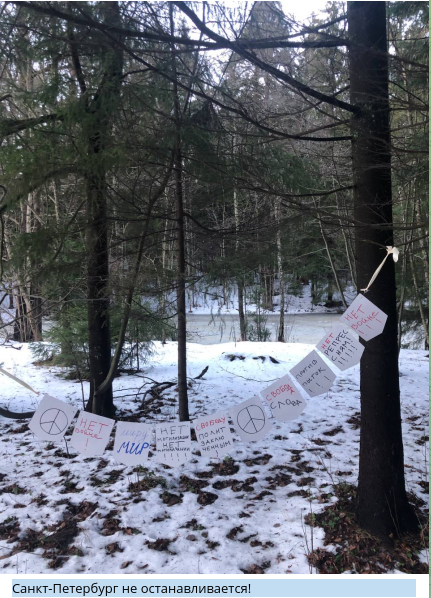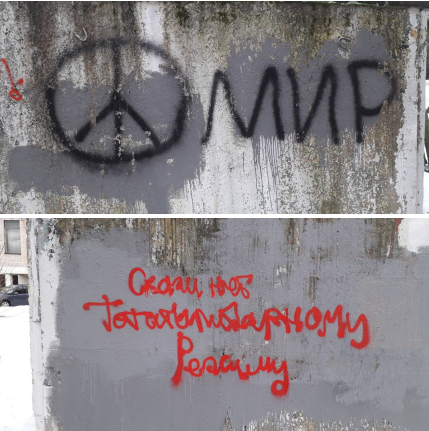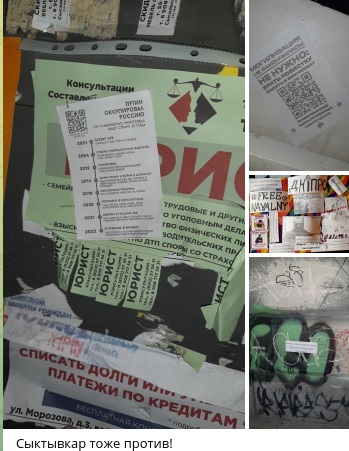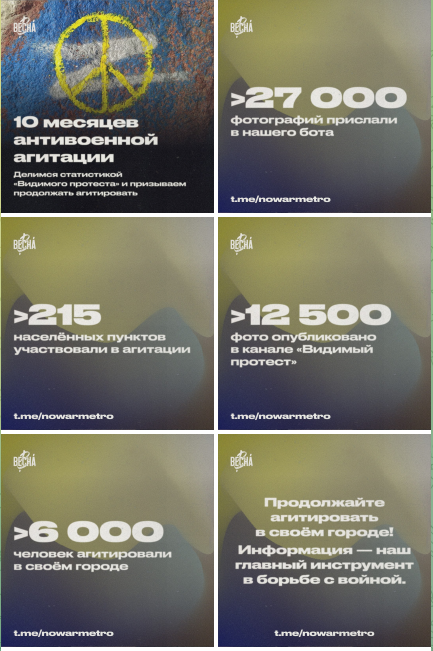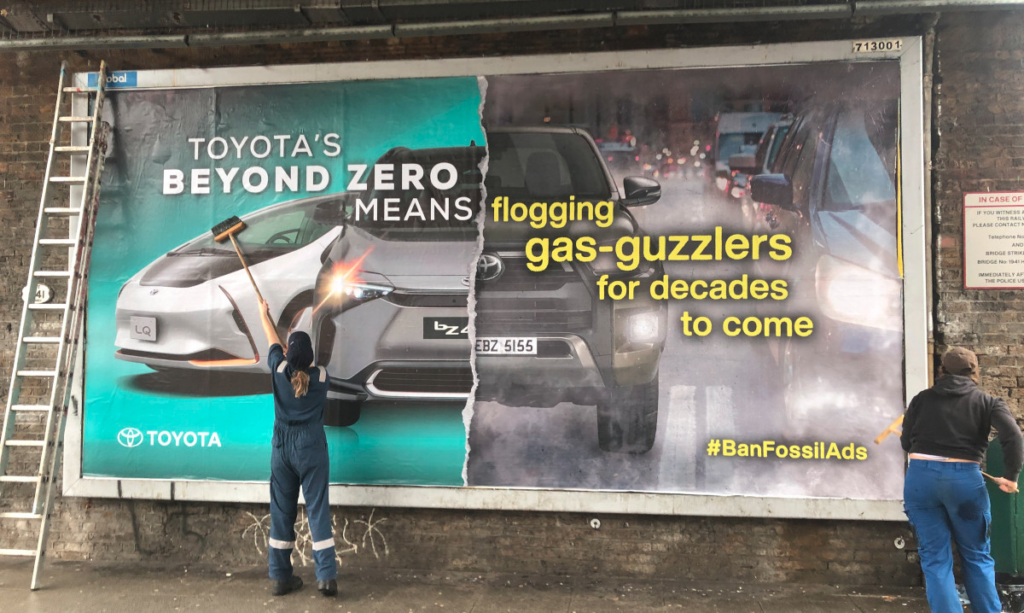JCA-NETセミナー2023年5月のお知らせ
私が主宰するJCA-NETの月例セミナーがあります。初回参加に際しては申し込みが必要です。下記の案内の最後をごらんください。
____________________________________
JCA-NETセミナー2023年5月のお知らせ
JCA-NET (2023/5/7)
____________________________________
Table of Contents
_________________
1. セミナー1 5月24日(水) 19時から ChatGPT:政府と企業の動向とその批判
2. セミナー2 5月27日(土) 15時から NATOのサイバー軍と日本の自衛隊
3. セミナー3 日時:5月30日(火)19時から フォローアップ
4. 参加方法
1 セミナー1 5月24日(水) 19時から ChatGPT:政府と企業の動向とその批判
====================================================================
開催方法:オンライン(申し込み方法は最後をごらんください)参加費:無料
3月に続いてChatGPTを再度とりあげます。ChatGPTの「ブーム」といってもい
いような加熱ぶりが続いています。行政や教育への導入や民間企業の開発など
が野放しですすむ一方で、問題点の指摘も増えてきてはいるものの、規制の議
論も国益や企業に思惑などが先行して私たちのコミュニケーションの権利を中
心に据えての議論はまだ十分ではないように思います。
また「対話型AI」とも呼ばれて、あたかのChatGPTとの対話を人間との対話に
なぞらえて話題にすることへの疑問がほとんど見受けられません。学校現場で、
教師が子どもたちと対話することとをCHatGPTに置き換える教育システムが安
易に発想されているようにもみえます。また、住民の行政との交渉、消費者や
労働組合の企業との交渉など、私たちの権利行使にとって、対立する利害当事
者との交渉は重要な役割を果しています。こうした交渉をChatGPTに委ねたり、
更には裁判などへの導入も海外では現実になっています。そして、これまで繰
り返されてきた、機械化=合理化という資本主義の基本的な構造を視野に入れ
た議論はまだまだ不十分でしょう。
そもそも人間にとっての「対話」とはどのようなことなのか、人との対話と人
工知能との対話を同じように扱うことはできるのか、あるいは、人と同じよう
に扱うことが社会的に広く採用されることによって私たちの価値観や信条、感
情などにこれまでにはみられなかった問題を引き起すリスクはないのでしょう
か。しかも、こうした「対話」の過程が、同時に私たちのコミュニケーション
に関するデータの収集手段になることによって、私たち一人一人の考え方や行
動を予測するなど監視社会の手段として利用しうる危険性もありえます。
これら諸々の問題点を、最近の議論や政府などの動向を紹介しながら参加者の
皆さんと議論します。
参考資料検索:ChatGPT (電子政府窓口)電子政府窓口の横断検索(Google)で
「ChatGPT」で検索した結果
<https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/lsearch_chatgpt-gov/>
検索:ChatGPTに言及している政府関連サイト(DuckDuckGo検索)
<https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/chatgpt_duckduckgo_gojp/>
(CDT)人工知能がトップニュースを席巻している。
<https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/cdt_spotlight_on_ai/>
(NT) ノーム・チョムスキー ChatGPTの偽りの約束
<https://www.alt-movements.org/no_more_capitalism/hankanshi-info/knowledge-base/nt-noam-chomsky-the-false-promise-of-chatgpt/>
AI-GPT: a game changer? by Michael Roberts(英文ですが当日までに日本語
訳を準備します)
<https://thenextrecession.wordpress.com/2023/04/08/ai-gpt-a-game-changer/>
2 セミナー2 5月27日(土) 15時から NATOのサイバー軍と日本の自衛隊
===============================================================
開催方法:オンライン(申し込み方法は最後をごらんください)参加費:無料
4月に防衛省はNATOサイバー防衛協力センターへの正式参加を表明しました。
すでに防衛省・自衛隊は同センターに職員を派遣し、2021年以降、同センター
が主催の大規模なサイバー防衛演習「ロックド・シールズ」に正式参加し、今
年は井野防衛副大臣まで視察参加しています。また、この演習には軍関係者だ
けでなくNTTなどIT企業大手や警察、セキュリティ関連の政府機関など幅広い
分野からの参加も特徴になっています。また、同センターは「タリンマニュア
ル」と呼ばれる事実上のサイバー戦争の国際法の枠組も公表し、サイバー領域
の戦争を主導しようとしてきました。戦争に関連する国際法秩序を軍関係の組
織が主導することは極めて危惧すべき事態です。
サイバー戦争はいわゆる「ハイブリッド戦争」の一環として、軍事と非軍事、
戦時と平時にまたがり情報通信全体を戦争や国家安全保障の枠組で統制するきっ
かけになります。しかし、前回のセミナーでも議論したように、サイバーの領
域は日本の反戦平和運動にとっての脆弱な領域です。平和運動が弱い領域であ
る分。逆に政府はフリーハンドで戦争への加担にのめりこんでいるように思わ
れます。今回のセミナーでは日本の動向に焦点をあてながら、官民を巻き込む
サイバー戦争の現状を知るとともに、サイバー戦争放棄のための反戦平和運動
の取り組みの課題を参加者のみなさんと議論します。
参考資料防衛省:NATOサイバー防衛協力センターの活動への正式参加につ
いて<https://www.mod.go.jp/j/press/news/2022/11/04b.html>日経:NATOが
東京に拠点 2024年、サイバーなど協力強化。対中ロにらむ 自衛隊の演習参
加検討<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR05ETO0V00C23A4000000/>
(Twitter)井野防衛副大臣「ロックド・シールズ2023」視察
<https://twitter.com/ModJapan_jp/status/1650807723146252288> (プレスリ
リース)国際サイバー防衛演習「Locked Shields 2023」に NTT グループが参
加<https://group.ntt/jp/newsrelease/2023/04/19/pdf/230419aa.pdf> NATO
military delegation heads to Japan for staff talks
<https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_214295.htm?selectedLocale=en>
3 セミナー3 日時:5月30日(火)19時から フォローアップ
====================================================
オンライン(申し込み方法は最後をごらんください)参加費:無料
毎月最後の回は、これまでのセミナーで取り上げたテーマの積み残しや、うま
く解決できなかった課題、あるいは皆さんが抱えている疑問や問題を出し合っ
て解決していく回になります。とくに、Linuxを新規に使いたい、WordPressで
のブログの作成方法などについて今年に入ってから問い合わせをいただいてい
ますので、これらについても、このフォローアップの場で簡単な説明を行い、
個別の対応もしたいと考えています。またEmotetの再流行の兆しもありますの
で、マルウェア対策についての質問などもあればお寄せください。この他、気
軽に、日頃抱えている問題などがあれば、ご発言ください。
技術的なテーマとして、これまでセミナーで取り上げてきたものの一例。
– Mastodonの使い方
– パスワード管理
– WordPressによるブログの設置
– Jitsiを使ったオンライン会議
– 暗号化サービスProtonやTutanotaのメールサービス
– 機械翻訳の活用(DeepL)
– LinuxOSの導入と活用
– ブラウザのプライバシー、セキュリティ設定
– Internet Archiveの使い方
– CryptPadの使い方
など。
最近の社会・政治的なテーマでセミナーやメーリングリストなどで話題になっ
た事柄の一例。
– 安保・防衛3文書とサイバー
– ChatGPT
– スマートシティ
– マイナンバーとデジタルID
– インターネット遮断
– 政府による暗号規制
– ミャンマー軍事政権とネット監視
– ジェンダーとインターネット
など。
4 参加方法
==========
参加費 無料(カンパ大歓迎)
オンラインはJitsi-meetを使用します
オンライン会議室 Jitsi-meetのマニュアル
<https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/93>
参加方法:JCA-NETの会員メーリングリスト、セミナーメーリングリストに登
録されている方は、当日30分前に、メーリングリストからの会議室案内をみて
アクセスしてください。
JCA-NETの会員以外の方でセミナーに初めて参加される方は予約が必要です。
おなまえ、メールアドレス、参加希望のセミナー番号(複数可)を書いて、下記
に申し込んでください。
jcanet-seminar@jca.apc.org
あるいは下記の申し込みフォーム(cryptpadのサイト)から申し込むこともでき
ます。
<https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/wOn2i-IivABy0Y7+FMRiua+rzzWxIiQm44Btv2h3F+Q/>
—–
余裕のある方は是非カンパをお願いします。
セミナーはJCA-NETの会員の会費で運営されています。
郵便振替口座
JCA-NET (シ゛ェイシーエイ-ネット )
記号番号:00190-3-417584
ゆうちょ銀行〇一九店 417584
通信欄に「セミナーカンパ」とお書きください。
問い合わせ先
小倉利丸(JCA-NET理事)
toshi@jca.apc.org
070-5553-5495