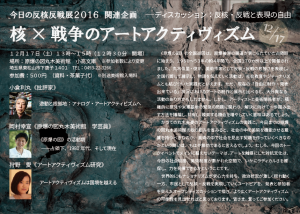米大統領選挙が露呈させた国民国家と民主主義のもはやこれまで!
今回の米国大統領選挙ほどグローバルな資本主義のもとでの国民国家における民主主義が、明確にその限界を露呈したことはなかった。もともと国民国家は、階級構造が生成してきた搾取の構造を「国民」という普遍的価値を装って均質なアイデンティティを扮装することによって隠蔽する仕掛けでもあった。しかし、資本蓄積の構造(言い換えれば搾取の構造)が否応なく資本の出自を越えて(あるいは資本の出自を裏切って)展開しないではいられないほど成長=肥大化するなかで、自国とその外部という国民国家の境界に沿って、自国内の階級構造がもたらした失業や貧困の矛盾を、外部の「敵」に転嫁し、この「敵」と内通する自国内の既得権益に固執する特権層や、境界を密かに越境して「非合法」に自国の富や雇用を脅かす自国内部の他者にその責任を転嫁し、有権者である特権的な犠牲者の地位を白人労働者階級に付与するという構図が今回の大統領選挙を席巻した。トランプ陣営は白人労働者階級の一部が抱く人種的優越主義を刺激しながら「偉大なアメリカ」というイメージを構築するプロパガンダを展開した。トランプのプロパガンダは、伝統的な共和党のイデオロギーと相入れないだけでなく、これまで既成の政治を嫌ってきた下層の保守主義を代表すると言われてきたリバタリアニズムとも異なるスタンスをとった。とりわけリバタリアンが強調してきた小さな政府と自由競争資本主義への信仰(ハイエクやフリーッドマンなどだが)を否定した点は、それがサンダース支持者の取り込みという戦術の一環であったとしても、そのプロパガンダの方法も含めて、これまでの米国政権のなかで最もファシズムに近似する性格をもった主張であったという点に特徴があったといえるかもしれない。
国民国家の民主主義の限界は、グローバル資本主義がもたらした世界規模での貧困と紛争の根源にある米国の覇権国家としての責任という問題を正面に据えることができないという点に現われている。更に悪いことに、この問題が米国内の貧困問題に還元された上に、この原因をもっぱら外部の他者(中国であったり「不法移民」であったり、いずれにせよ有権者ではない国民国家にとっての他者)になすりつけて、愛国心を鼓舞するという方向でしか選挙のキャンペーンは展開されなかったということだ。国内の有権者のみを対象とする国政選挙という枠組は、米国ナショナリズムの神話=「偉大なアメリカ」のイデオロギーを再生産し、国民的な一体性や同質性を確認するための儀礼効果として、常に、外部の敵を再生産することに終始せざるをえない。これは国民国家の民主主義にとって解決困難な難問であって、米国に固有の問題ではない。これは近代国民国家と憲法が本質的にもっている敵対の構造に基づく自己保存の権力メカニズムであり、人びとの生存を脅かす根底をなすものの一つでもある。
●
米国大統領選挙でトランプは、失業と貧困から脱却できない主として白人労働者階級の票を獲得したのではないかと言われている。彼は、中国やメキシコに製造業が流出し、米国製造業を支えてきた錆びついた工業地帯(rust belt)と呼ばれる地域の白人労働者階級の職を取り戻すと主張して、TPPに反対し、安価な賃金で貿易で優位に立つメキシコや中国を非難してきた。ペンシルベニア、ウェストバージニア、オハイオ、イリノイ、アイオワ、ウィスコンシンといったかつて重工業で栄えた地域は、イリノイを除いて全てトランプが勝利した地域だ。一般論として、日本でもよく聞かれる主張として、新自由主義グローバリゼーションによって国内の産業が海外に移転することによって、職が奪われ格差と貧困がより深刻になる、だから自由貿易には反対だという議論の立て方がある。こうした主張は間違いではないが、正しいわけでもない。どこの国であれ、新自由主義の政権を批判する野党が、自国の有権者だけを念頭に陥いりがちな自覚されない排外主義のスタンスであり、格差と貧困に直面している有権者には実感をともなう主張だとして受け入れられやすいのだが、同時に、有権者の大衆意識としても、自分達の職を奪う「他者」像を構築してしまう。これは、自国内の移住労働者や近隣諸国の低賃金労働者への感情的な敵意を醸成しかねず、これが感情的なナショナリズムを支える基盤をなす危険性をもつことになる。
ナイジェリア出身で米国在住のアフリカ史の研究者モーゼス・E・オチョヌは、「新自由主義グローバリゼーション、白人労働者階級、アメリカ例外主義」(注)というエッセイで、米大統領選挙において、米国労働者階級がグローバリゼーションの被害者であるといことを強調する論調には、米国を特別視する価値観、言いかえれば、「米国の労働者階級だけがグローバル化における敗者となっており、それ以外の人びとは新自由主義の利益享受者だ」とする誤った見方が支配的であったと指摘した。こうした見方には「ナイジェリアのイルペジュ(Ilupeju)カドゥナ(Kaduna)、カノ(Kano)など、破壊された工業センターにおけるグローバリゼーションの被害者たちへの同情も連帯もみられない」と批判した。ナイジェリアでは、ここ15年の間に、グローバル化によるアジアからの安価な繊維製品の流入で国内産業が大きな打撃をこうむってきた。こうした事例は「南」の諸国で広範に見られる新自由主義グローバリゼーションがもたらした悲劇だ。
(注)Moses E. Ochonu, “Neoliberal globalization, the white working class and American exceptionalism”
しかし問題の構造はもっとやっかいで、中国やインドはアフリカとの関係ではアウトソーシングのハブとして機能しており、これら諸国との経済的な格差と資本投資による搾取の最底辺をなすのがアフリカ諸国になるグローバル資本主義の階層構造がある。この全体の構造を支配しているのは、言うまでもなく欧米の多国籍資本である。オチョヌはこうした構造を無視すべきではないとし、だからといって、中国の工場労働者がグローバル化の勝ち組の側にいるわけでもないことを強調する。だから、米大統領選挙で強調されたグローバル化によって職を奪われたという場合、アフリカ諸国は米国の職を奪える位置にはなく、むしろグローバル化の犠牲者でありつづけた。オチョヌは、アフリカの視点からすれば、米国労働者階級をもっぱらグローバル化の犠牲とみなす観点には同意できないとし、「 世界中で、多くの人びとは、米国の労働者階級同様、新自由主義的グローバリゼーションの収奪のなかで尊厳を維持しようと闘っている」ことを強調した。
当然のことながら、米国大統領選挙で主張された格差、貧困の問題ではこうしたグローバルサウスが被ってきた犠牲への関心はほとんどみられなかった。なぜなら、アフリカの人びとは有権者ではないからだ。しかし、米国の新自由主義グローバリゼーションの被害者であり利害当事者であることもまた明かだ。この排除を正当化しているのは、憲法の枠組であり、国民国家に基づく民主主義なのだということを軽視することはできない。ちなみに、ヒラリーよりずっとマシなバーニー・サンダースですら、自由貿易の問題は低賃金諸国が「アメリカの労働者」「わが国の労働者や中産階級」から職を奪うことだというスタンスが基本にある。(サンダースのTPP反対演説「TPPに反対する四つの理由」は議会演説としては優れていると思うが、国境を越える連帯の視点を持てない限界はいかんともしがたい。)
外交や安全保障から経済まで、閉鎖的な国民国家など存在しないにもかかわらず、絶対多数の利害関係者(米国の選挙権を持たない米国内外の人びと)を排除した上で行なわれる選挙のどこに正統性があるといえるのか。グローバル資本主義に対する米国の責任という観点から大統領選挙が争点化されることはまずありえない。これは米国に限らず一般論として言えることであり、国民国家によって分断されて選挙の権利がナショナルなアイデンティティを共有する人口に限られるなかで実施されることによって、民主主義はナショナリズムを正当化し、その結果として国民国家相互の摩擦や敵対を根本的に調整することが困難な条件を抱え込むという近代国民国家のリスクを体現するシステムだからだ。しかも、こうした利害の当事者の排除に基づくナショナリズムが正当化される一方で、資本は容易に国境を越えてグローバルな投資環境を構築しようとし、各国政府もまた、自国資本のグローバルな展開を相手国当事者を排除した民主主義的な合意形成によって正当化する。こうした国民国家の枠組に規定された民主主義選挙の争点から排除される論点は、一国内の有権者の利害に関わらないが世界の民衆にとっては死活となる課題である。あるいはグローバルな民衆の問題をあたかも一国内の特定の階層にのみ関わる問題であるかのように論点を歪曲した上で、これを正当化するレトリックの技術の横行である。民衆はどこの国であってもいったん「国民」として自己のアイデンティティが再定義されて内面化されると、相互に敵対関係の枠組の中で相手を見ること以外の眼差しを持つことが心理的にも困難になる。
直接間接に利害をもつ人びとが国境や国籍を越えて討議できる枠組がなくナショナルなアイデンティティに傾き、グローバルな公正性(といった近代コズモポリタニズムが掲げる理念)すら脇に追いやられる構造の根源に、皆が大切だと信じている憲法制度(立憲主義と呼んでもいい)の存在があると考えている。憲法は、普遍的な価値を国家の理念として立てる一方で、主権者を国籍によって排除・選別する。この枠組の境界線上に、移住労働者、難民、外国籍の人びととして、膨大な数で地球上に存在する。一国が有する他国との利害関係のなかには、主権者としての権利をもたない多くの人びとの利害もまた含まれる。現実の人口構成と憲法が規定する権力の正統性を支える民主主義の基盤をなす人口との間には無視できないズレと亀裂がある。トランプの「壁」発言は、この亀裂が民主主義の正統性の危機の域に逹っしていることを端的に示したものと解釈できるかもしれない。更に、分離独立を求める集団が存在する国が少なからずあり、こうした分離派にとっては憲法は、分離を妨げる最大の規範となる可能性がある。こうした状況と、憲法を後ろ盾とした資本や軍隊の越境性とを比較したとき、一体どこに民主主義の効用が、あるいは憲法の普遍性についての肯定的な価値があるというのだろうか。
今回の米国大統領選挙は、国民国家という枠の内部で競われる民主主義的な選挙が同時にナショナリズムを高揚させて、人種差別主義を正当化する危険性があることを端的に示した。トランプのように「偉大なアメリカ」を口に出して叫ぼうが、ヒラリーのように「偉大なアメリカ」を暗黙の前提としようが、彼らが競っているのは、どちらが「偉大なアメリカ」を将来において維持あるいは再現あるいは再興できるのかでしかない。彼らにとって、米国民(つまり有権者だが)の犠牲を最小化し、その利益を最大化するための政策を競っているのであって、この方程式の解が、他国の犠牲を最大化し、その利益を最小化することがあってもそれは問題の焦点にはならない。このことを端的に示したのがトランプによる米国白人労働者階級の貧困問題への言及だっただろう。彼にとって米国白人の貧困は特別に重要な解決されなければならない問題だということであり、この立場を支持する米国の有権者が少なからず存在したことがトランプの勝利を支えた。トランプだけでなく米国の有権者の多くも、米国の国民は例外的に繁栄を享受する権利があるかのように感じているのではないか。
●
一世紀近く前の古い話をしたい。カール・シュミットは『現代議会主義の精神史的地位』(稲葉素之訳、みすず書房)の第二版(1926年)まえがきで次のように述べている。
「あらゆる現実の民主主義は、平等のものが平等に取扱われるというだけではなく、その避くべからざる帰結として、平等ではいものは平等には取扱われないということに立脚している。すなわち、民主主義の本質をなすものは、第一に、同質性ということであり、第二に──必要な場合には──異質的なものの排除ないし絶滅ということである。このことを説明するためには、民主主義の二つの異った例について一言するだけで十分であろう。すなわち、一つは今日のトルコがギリシア人を徹底的に国外へ移住させることによって、その国土をトルコ化しようとしていること、他の一つはオーストラリアの_くに_(Gemeinwesen)が移民立法によって好ましくない移住者の流入を阻止し、他の自治領と同様に、_正しい種類の植民者_に合致する移住者のみを入国させていることである。すなわち、民主主義の政治的力は、他所者と異種の者、すなわち同質性を脅かすものを排除ないし隔離できる点に示されるのである」(14ページ)
上でシュミットが言う同質性とは「一定の国民への帰属性、すなわち国民的同質性」を意味するとともに「一般に民主制には、これまで常に奴隷または野蛮人、非文明人、無神論者、貴族あるいは反革命分子と呼ばれる何らかの形態で全部のまたは一部の権利を剥奪され、政治的権力の行使から除外されている人間が常に附きものになっていた」(15ページ)とも述べている。
シュミットにとって国民的同質性の核をなすものは、「民族的に同質な国家」であり、「大抵の国家は、それ自身の内部においては民族的同質性に基づいて民主主義を実現しようと努めているが、その他の点ではあらゆる人間を同権的な市民として取り扱っているわけではないのである」(17ページ)とも述べている。
シュミットは後にナチスの同伴者になるが、ワイマール時代に彼が論じた論点は今に至るまで繰返し議論の対象になってきた。ここで述べられている論点は、民主主義を擁護しようとする者たちにとっては実は聞きたくない考え方だろうと思う。しかし、民主主義が合意形成の手続きである以上、その前提として共通の価値規範を何か持たないことには成り立ちようがなく、そうであるとすると、価値観を共有しえない部分を排除するメカニズムを持つことによって民主主義的な合意形成を効果的に発動できるような制度設計が不可欠になる。国民国家は、これを「国民」としてのアイデンティティとして形成・再生産しようとするとともに、国家権力を制約する規範を「普遍的な価値」として構成することによって、理論上は何人も否定できない価値に基づく「同質性」を標榜することになる。これは多様性や異質なものの排除を意味するのではなく、これらを包含することを前提として形成される合意こそが普遍的な価値の体現であるとすることによって、同質性を異質なものの同質性として立てうることを示そうとしてきた。その結果、政治は言説のレベルにおける普遍的な価値の氾濫の一方で、現実には、普遍的な価値に名を借りた差別と排除が横行することになった。差別ではなく正当な競争の結果であるとか、排除ではなく普遍的な価値を実現するための秩序の実現であるなど、権力は政治の言説を討議に基く真理への過程としてではなく、既存の権力を正当化するためのレトリックと駆け引きのための詭弁として用いてきた。
憲法はこうしたレトリックの中枢をなす普遍的価値の擬制の体系なのだが、憲法が支えられているメタレベルでの権力の自己再生産構造を見ずに、憲法の条文が意味するであろう内容を「憲法学」的に解釈する立法府やアカデミズムの議論は、実は憲法が、普遍的な価値を纏うが故に逆説的に暗黙のうちに含んでいる排除の正当化の機能を見落している。シュミットはこの点を突いて、民主主義は排除と同質性の維持、とりわけそれを民族的同質性以外にはありえないと断定することによって、ワイマールとナチズムを同じ土俵の上で正当化してみせたのだと言うことができるかもしれない。ワイマールはよくてナチズムは悪いというふうには問題はたてられないのだ。同じことは、米国憲法にもいえる。トランプを生んだのは米国憲法であり、安倍を生んだのは日本国憲法なのだ、という事実から、憲法や国民国家という権力の構成を免罪できるか、という問いを私たちは自問しなければならないところに立っている。
●
米国大統領選挙から見えることは、日本の政治や国家の制度の問題とほぼ重なる。民主主義の欺瞞であれ、憲法のレトリックであれ、これらをシニカルに捉えて諦めるのではなく、だからこそこれまでにありえなかったような社会を構成する基本的な枠組を構想するという問題に挑戦しなけらばならないということではないのだろうか。「日本」やこの国のナショナリズムを廃棄するという課題は世代を越える大きな問題だが、この問題に答えを見出せないとすれば、国民国家が本質的に抱えもっている生存に対する危機を座して覚悟するという選択しか残されないと思う。それでいいはずはない。