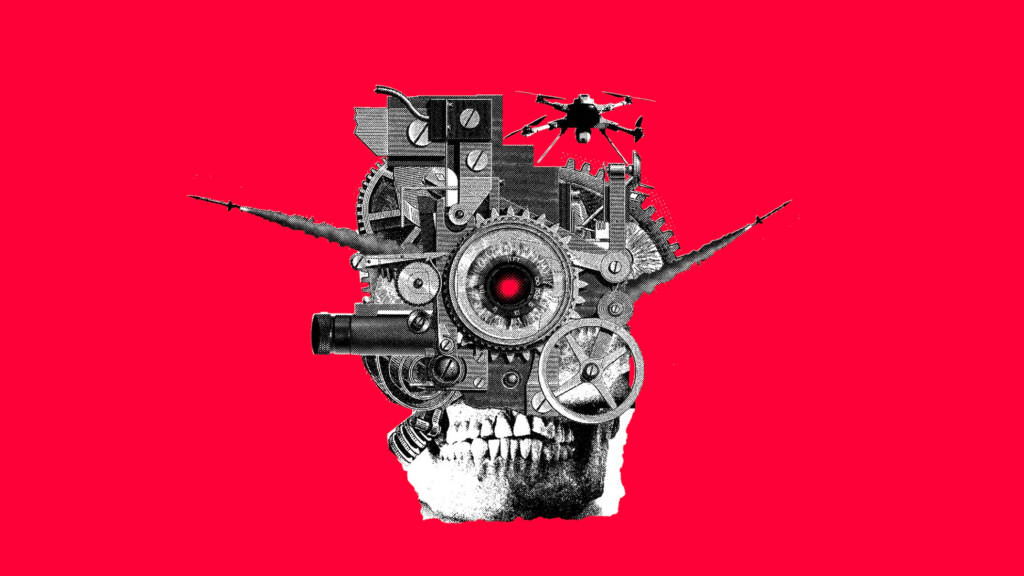戦争放棄のラディカリズムへ――ウクライナでの戦争1年目に考える戦争を拒否する権利と「人類前史」の終らせ方について
Table of Contents
- 1. ウクライナ戦争の影響
- 2. 防衛予算は「ゼロ回答」以外に選択の余地はない
- 3. 国家と民衆の利害は一致しない
- 4. 難民について
- 5. 暴力についての原則的理解
- 6. 9条の限界と戦争放棄の新たなパラダイム
- 7. 二人のファノン――締め括りのためのひとつの重要な宿題として
- 8. 参照文献
1. ウクライナ戦争の影響
日本の主な平和運動がロシアの侵略とウクライナの抵抗から受け取った教訓は、戦争放棄の徹底ではなく、侵略を阻止するための自衛のための戦力は必要だ、という観点だ。この観点は、憲法9条の改憲に反対する多くの平和運動の側が、自衛隊を専守防衛であれば合憲とみなす憲法解釈を支持してきた経緯の延長線上にあり、その意味では目新しいものではない。かつて反戦運動のなかで無視しえない有力な主張として存在していた非武装中立論が主流の平和運動ではもはや主張されることがなくなってしまった経緯や、更にもっと遡って、憲法制定当時の与党の憲法解釈がそもそも武力による自衛権を違憲とする解釈をとってきたにもかかわらず1、自衛隊の創設とともに、こうした議論はもはやとうの昔に、保守派のなかでは見出されなくなった。おなじ条文がこれほど真逆な解釈を可能にしているのは、憲法というテクストの解釈それ自体が唯一絶対に正しい解釈を獲得できず、常に権力者が――政府、裁判所、有力なアカデミズム――解釈の主導権を握ってきたことの証明でもある。この意味で日本は、法の支配の下にあるのではなく、法を超越する権力によって支配された社会なのだ。他方で反戦平和運動は、自衛隊が自明の存在になり、その廃止などは非現実的な要求であるとして要求項目にすら入らなくなるになるにつれて、戦争放棄は、ひとつの建前あるいは立場表明のための単なるスローガンとなっている。理念や理想を現実の世界に持ち込むことよりも、理念なきリアリズムの政治――選挙の得票数に還元される政治であり、この数字こそが政権を獲得する唯一の手段だとする政治――の罠に置い陥ってきたようにおもう。これで戦争に反対できるのだろうか。いかなる事態に陥ろうとも戦争という手段をとらない、という断固とした決意をどうしたら取り戻せるのだろうか。
2. 防衛予算は「ゼロ回答」以外に選択の余地はない
先制攻撃や敵基地攻撃能力の保有に反対することが現在の反戦平和運動の主要な関心であることに私も同意するし理解できるが、他方で、この主張と表裏一体をなすようにして、専守防衛であれば戦力を保持せずに武力による威嚇にもならずに9条の戦争放棄条項に抵触しないという含意があるのが一般的かもしれない。自衛隊の存在それ自体を容認した上での先制攻撃や敵基地攻撃能力保有反対は、私とは相容れない主張になる。自衛隊それ自体の是非を論じることを回避して、自衛隊の存在を暗黙の上で肯定して防衛予算の規模に着目し、GDP2パーセントはケシカランといいつつ1パーセントなら構わないかのような値切交渉に主な関心が移っているようにも思う。だから「軍拡反対」という場合も、自衛隊の専守防衛を容認して、ここからの逸脱としての「軍拡」に反対するのは、そもそも私にとっては受け入れがたい前提になる。自衛であれ先制攻撃であれ、戦車や戦闘機や武器弾薬の使用価値は、人を殺すことにあるから、防衛予算は人殺しの武器を買う予算なのだ。国家予算を使って人殺しの道具を買うべきではない、だから予算などつけるべきではない。防衛予算は「ゼロ回答」以外に選択の余地はない、これが平和主義が出すべき唯一の回答であるべきだ。だから防衛予算2パーセント反対を強調することによる誤解(1.5パーセントならいいのか、といって議論の矮小化)を避けるべきであって、防衛予算を計上するな、という原則を繰り返すべきなのだ。こうしたことが反戦平和運動の側がとるべき原則だと思うが、このような声はなかなか聞かれなくなっている。
そもそも私は、軍事領域で自衛に限定した武力行使で勝利することはまず不可能だとも考えている。戦闘が継続し、長期化すれば自衛と攻撃との区別をつけることはできない。自軍の犠牲を最小化するための攻撃の手段は、多くの場合、空爆やドローン攻撃など非人道的な武器の使用に依存することになる。その先に核の使用がありうることは誰にもわかることだ。
ロシアの武力による侵略は容認できないという点では、反戦平和運動に共通の了解があると思うが、対するウクライナによる武装抵抗やNATOをはじめとする西側の軍事支援については、賛否が分かれていると思う。ウクライナによる武装抵抗を暗黙のうちに支持し、その系論としてNATOや西側による軍事支援についても支持する立場をとる人たちもいる。戦争が長期化し投入される武器を高度化させてでも領土の完全奪還とロシア軍の撤退を譲れない線だとする立場をとる場合、NATOなど外国の兵器供与や軍隊による介入を否定する論理は見出しにくい。他方でNATOや米国のウクライナの戦争に懐疑的あるいは批判的な立場をとるという場合、これまでNATOや米国が繰り返してきた戦争や戦争犯罪からすれば、それ自体としてはまっとうにみえる主張であっても、ロシアによるウクライナへの侵略行為にほとんど言及しないというケースがありうる。たとえば2月19日にワシントンで開かれたRage Against the War Machineという集会ではNATOやCIAの解体やウクライナの戦争に税金を使うな、など10項目の要求を掲げているが、ロシアへの批判はほとんどみられない。2 この集会は、右派が左派の一部を巻き込んである種の反戦平和運動の統一戦線の体裁をとろうとしたもののように見える。私はこうしたスタンスにも懐疑的だ。
私は、プーチン政権の侵略を正当化する理屈を見出すことはできない。他方で侵略の被害者のウクライナの政権や軍部が正義の体現者だと評価することも難しいというのが私の見方だ。私は、暴力を行使した順番とか暴力の残虐さの程度とか、戦争を肯定した上での国際法違反とか、こうした様々な暴力(武力)行使の正当性がありうるという前提には立たない。後に述べるように、問題解決の手段としての暴力の正当性を認めないからだ。他方で、戦争を終結させるための様々な和平の可能性を探ることについても、実はあまり関心がない。和平の問題は権力者たちが正統性のある意思決定の手続きを伴いながら対処することであり、彼らが実際に軍の指揮権をもっている以上、彼らの動向は重要だが、彼らが言葉にする和平や正論にみえるようなメッセージも、近代国民国家の権力構造のなかから権力の力学による政治的な思惑や計算によってはじき出される「答え」であって、おなじ言葉に民衆が込めるであろう意味とは同じにはならない。私のように、政治評論家や政治組織に属さない者にはうまく論じることができない。関心があるのは、むしろ、戦争が継続している今、戦争に背を向けて戦場や戦争当事国から避難しようとする人達や、兵役を忌避したり軍隊から逃亡するなど、様々な手段で戦争に抗う人達だ。
メディアは毎日のように、中国、ロシア、北朝鮮を不条理な侵略者として報じている。人々は、日本をウクライナと重ねあわせて、侵略される恐怖を抱くような感情が形成されている。同様の不安感情は韓国にもいえるために、韓国では核武装論まで登場しはじめているという。こうして、ウクライナの戦争は、地域の人々の間に心理的な分断と敵意を醸成してしまった。他方で、日本がロシア同様、不条理な侵略者となる可能性を秘めていることにはまったく気づいていないように思う。日清、日露の戦争から1945年に終結した戦争まで、日本の戦争は常に、自衛を口実とした先制攻撃と侵略だったことを皆忘れてしまったようだ。だから、この国で専守防衛と敵基地攻撃の差を議論することにはあまり意味がない。国家の防衛という観点で領土や権益を推しはかろうとする地政学イデオロギーが突出する結果として、犠牲になるのは、権力者や金持ちではなく、関係する諸国・地域の民衆だ、ということが最大の問題なのである。日本の場合、沖縄はまた再びヤマトによって犠牲にされかねないのが「自衛」とか「専守防衛」の意味している現実的な内容だ。専守防衛を肯定する本土の平和運動は、このことをどのように理解しているのだろうか。
3. 国家と民衆の利害は一致しない
「日本が理不尽に他国から侵略されても、あなたは日本を守るために戦うつもりがないのか?」とよく問われる。私は、「国家間の諍いに私を巻き込まないでほしい」「It’s not my business」と考えるので、私には日本を守るという発想はない。そもそもこうした問いの前提にある「日本」や「日本人」という言葉に私は翻弄されたくない。私という存在を可能な限り、国家の利害から切り離したい。そのためには、私を日本人というアイデンティティのなかに押し込めて、国家のアイデンティティに収斂させるように作用する言説や心理と闘う必要がある。
戦争では、問題を、国家レベルで把えざるをえないように仕向けられる。あるいは、戦争をプーチンに代表されるロシア、ゼレンスキーに代表されるウクライナという単純化された枠組で把える傾向がある。中国といえば習近平、朝鮮といえば金正恩で代表させて政治を論じると、それぞれの国のなかで暮すひとりひとりの意思の多様性が無視されてしまう。こうした指導者=権力者をアクターとする国際政治の延長線上に国に分割されて色分けされた領土としての世界地図が描かれがちだ。わたしはこうした世界の論じ方、あるいは戦況を地図上に表示する陣取り合戦のような戦争の見方、あるいはひとりひとりの人間のかけがえのない命を単なる統計上の数字に還元して、どれくらいの戦死者までなら許容できるか、といった冷酷な数字の世界に加担したくない。
私は、武力による紛争の主体である国家と、それぞれの国のなかに暮す人々とは明確に区別すべきだ、と考えている。戦争とは国家による国家の都合で引き起こされる惨事であり、20世紀以降の国民国家では「国民」を主権者とすることによって国家間の戦争に「国民」とみなされる私たちが国家防衛に否応なく動員される理屈が支配的になった。わたしはこの意味での主権者としての国家防衛の義務を認めない。
ここで民衆の側に問われるのは、「私」という主体と私が帰属するとみなされている国家との関係だ。国家との自己同一化が強固であれば、「私」は国家の戦争を自らが命をかけて引き受けるべきものと感じるかもしれない。しかし、世界中の紛争地域で実際に起きているのは、多くの人々が武力=暴力を選択するのではなく、別の選択を必死で模索している、ということだ。地下で密かに隠れて戦闘が終息することを祈るか、わずかな可能性を求めて戦闘地域からの避難を試みる。自らの命を犠牲にするとしても、「敵」を殺すためではなく、誰も殺すことなくわずかな生き述びられる可能性を求めて場所を離れる。ロシアもウクライナも傭兵や強制的な徴兵に依存するのは、多くの人々が戦争という手段を望んでいないことの表れだ。このことは、近代国民国家において否応なく「国民」として主権者の義務を負わされるとしても、自らの生命をも犠牲にする義務や、「敵」を暴力(武力)によって殺害するという手段の行使を強制される、というところにまでは及ばない、ということを示してきたのだ。つまり、多くの民衆は、法や道義などではなく、むしろ民衆の生存の権利が国家による死の義務を超越することをその実践において示してきたともいえる。キリスト教徒であれば、汝殺すなかれ、という神の命令が国家の命令を超越するという主張は、良心的兵役拒否の歴史のなかで繰り返し主張され、また、法的な制度化すら獲得されてきた。同時に無神論者や無宗教の場合も、人間の生存の権利が国家の死の命令(殺すこと、あるいは殺されること)に超越する普遍的な権利である、という確固とした意識が存在してきた。国家は戦争機械でもあるにもかかわらず、その理念において、生存を保障すべきものともされており、この相矛盾する両者のせめぎあいのなかで、民衆に問われているのは、生存の権利を国境を越えて普遍的なものとして主張すべきであり、そのためには戦争機械と化している国家を否定することに躊躇してはならない、ということだ。しかし、現在のロシアやウクライナにおける徴兵拒否者への扱いをみればわかるように、現実の近代国家は、国家の生存を人々の生存よりも上位に置き、人々の犠牲によって国家の延命を図ってきた。
現在のウクライナの戦争は、1年を経て、領土と主権のメンツのために、双方の死者の数がどれほど積み上げられるまでなら耐えられるか、といった残酷なチキンレースにしか私にはみえない。これは、領土をめぐる争奪という観点からみた最適な武力行使の選択でしかなく、人間の命の犠牲を最小化するための最善の選択肢ではない。ロシアもウクライナも、政権が執着しているのは「領土」であり、そこに住んでいる人々への関心が本当にあるのかどうか、私には疑問だ。もし、その場所に暮す人々が本当に大切な人々であるのであれば、その命を犠牲にするような暴力という手段を選択できないと思うからだ。ウクライナの東部に住みロシア語話者で前政権を支持していたような住民をキエフの政権が積極的に受け入れたいと思っていのだろうか。他方で、東部に暮すキエフの政権を支持する住民をロシアの占領者たちは、平等に住民として扱う積りがあるのだろうか。ロマや非ヨーロッパのエスニシティのひとたち、LGBTQ+の人達、こうした社会の周辺部で差別されてきた人達に、この戦争に勝利することが新たな可能性を与えるとは思えない。
4. 難民について
戦争放棄の最大の体現者は、戦場から逃れる難民たちや、戦火にありながら武器をとらずに、命懸けで日常生活を送ろうとする人々だ。法制度上でいえば、兵役拒否を裁判で闘うとか、軍隊からの脱走を選択する人達だ。こうした人達が実は戦時における多数者でもあるはずなのだ。ロシアについては、15万人以上の動員対象者が出国し、ウクライナから西欧に入国した兵役義務者が17万5000人、ベラルーシについては、出国した兵役対象者が2万2,000人という推計もある。国家にとってはこうした人達は厄介だが、むしろこうした生き方を選択する人々のなかに、グローバルな国民国家の統治機構が実現できなかった平和の可能性があると思う。兵役を忌避したり軍から脱走したり、様々な手段を使って武器をとらない選択をして国外に逃れた人達は、出身国にとっては自国の危機を見捨てた裏切り者になる。他方で、難民がたどりついた国にとってもまた、本来なら出身国に帰るべき余所者として扱われる。どちらの国にとっても、そこに住まう者に国家へのアイデンティティを要求しようとする限り、国家に背を向けて生きる人達は厄介な存在だろう。だから極右は、彼らを追い返し、出身国でナショナルなアイデンティティを構築することを求めるのだ。
戦争に難民はつきものだが、難民は上の議論からみたとき、その存在にはもっと積極的な意味を見出す必要がある。彼らは、戦うことによって現にある事態に決着をつけるという選択をしない人たちだ。むしろ、戦わない選択をするために場所を離れるという決断をすることになる。自分たちの暮してきた土地を捨てて、見知らぬ土地へと移動する。その先で受け入れられるかどうかすらわからない不安がありながらも、彼らは戦うことに命を賭けるよりも、転覆して遭難するかもしれないゴムボートを選ぶ。敵とされる人達を殺して、国家が求める領土のための戦闘よりも、誰も殺さないが自分は死ぬかもしれないリスクを負いながらわずかの可能性に賭けるのだ。これは彼らをあまりにもロマンチックに描きすぎているかもしれないが、本質的な事柄は、暴力に対する向き合い方をめぐる、戦場で戦うことを選択した人達との違いにある。この対比を踏まえて、戦争を忌避する人々の生き方のなかにこそ戦争放棄の思想が体現されていると思う。それに比べれば、自衛権や専守防衛などの武力行使の肯定を読み込んだ日本国憲法9条は、戦争放棄とは無援の単なる「絵に描いた餅」にすぎない。この実効性を失なった文言にひたすらしがみつくことが平和主義なのではない。もし9条が文字通りの意味で戦争放棄を具現化するものになるとすれば、戦争を選択した国家を捨てる権利、あるいは戦争を拒否する権利もまた基本的人権として明文化すべきだろう。つまり、日本の軍国主義を防ぐ最大の条件は、日本の民衆が武力を保有する国家に協力しないこと、 民衆が戦力の主体にならない、戦争を支えるあらゆる活動に非協力になれるかどうかだ。このことは、日本の民衆が、「日本人」という擬制のエスニシティに基くナショナルなアイデンティティからいかに自らを切り離せるか、にかかっている。
この観点からみたとき、日本は平和主義に対して世界で稀にみるほど背を向けてきた国家だということが見えてくる。なぜならば、日本はほとんど難民を受け入れていないからだ。戦争から逃れようとする人びとには手を差し出さない日本の態度は何を意味しているのだろうか。日本のナショナリズムの特異性から容易に外国籍の人々を受け入れられないイデオロギー上の枠組がある。この点はやや説明が必要かもしれない。日本の平和運動や伝統的な左翼やリベラルの一般的な認識は、戦前の日本の帝国主義は、1945年の敗戦によって終結したと評価し、戦後の憲法は、戦前の帝国主義からの決別という意義をもつものだと肯定的に評価する。だから、政権政党の自民党による改憲に対して現行憲法の擁護=護憲が基本的なスタンスになる。しかし、私の考え方はちょっと違う。戦前から戦後にかけて、日本は一貫して資本主義国家であり、この国家の基本的な性格には変化はない。この意味で戦前から戦後、そして現在に到るまで同じ支配の構造を維持している。したがってここにナショナリズムとしての一貫性を支える構造があり、それが極めて特殊な「日本人」としてのアイデンティティ構造として構築されてきた、ということだ。このアイデンティティの中心にあるのが天皇イデオロギーとでもいうべき特殊な集団的な収斂システムだ。この意味で、私は、戦後日本の戦前からの連続性を強調する立場になる。私は、この意味での近代日本を総体として否定する観点がないと、戦争を廃絶する社会を実現できないと考えている。
他方で、その裏返しとして、日本の「国民」が戦争状態のなかで、戦うことや戦争に協力することを拒否して「難民」として避難するという選択をとることについて、個人の自由の権利行使だとみなす考え方は、国家の側にも民衆の側にもほとんどみられない。その結果、避難の是非はもっぱら国家が一方的に決めることだとされるのが基本になり、個人の権利とみなされない。このことは、福島原発事故による放射能汚染から自主避難した人々がたどった苦難の道をみればわかることだ。
だから戦争状態になれば、「日本国民」は国家のために戦うこと以外の選択肢は事実上封じられるに違いないと思う。日本政府は、戦争になれば国家のために戦うのが国民の義務であり、逃げ出すなどというのは「国民」のとるべき道ではないという態度をメディアなどを含めて宣伝し、戦争(協力)を忌避する人々を追い詰め、時には犯罪者扱いすることになる。
もし平和運動が専守防衛を肯定してしまうと、こうした戦争を拒否する人達の権利を正当なものとして理解できなくなり、政府の戦争に暗黙のうちに加担する道を選択することになるのではないだろうか。日本政府が「平和国家」などを口にすることがあるが、これは欺瞞以外のなにものでもないことは反戦・平和に関心をもってきた人々には自明だが、他方で左翼の平和主義は、こうした移民・難民を受け入れない日本政府には批判的でありながら、日本の移民政策が平和主義に対する敵対的な態度であると明確に指摘して批判したことを私はあまり思いつかない。
戦争状態が現実のものになってしまったとき、平和運動は極めて無力な主張のようにみえる。戦闘状況のなかで、「平和」を主張することのむなしさは、容易に想像できる。しかし、だからといって、この無力さを理由に、暴力に対して暴力で対峙することが唯一の選択肢になる、と判断していいのだろうか。ここで、やはり、どうしても暴力とはいかない意味での解決の手段になりうるのか、という根源的な問いに立ち戻らざるをえなくなる。
5. 暴力についての原則的理解
近代において、暴力の廃棄は、国家と資本の廃棄と同義だ。暴力の廃棄は、人類の前史に終止符を打つ壮大な挑戦であり、この理想主義なしには平和を実現できない課題でもある。
暴力の問題について、私たちが確認しておかなければならない原則がある。それは、力の強い者が正義を体現しているわけではない、という事実だ。もし力が正義であるなら、ドメスティックバイオレンスでは、加害者である男の暴力が正義になる。力と正義の間には、何の論理的な因果関係も存在しない。
私たちが日常的に経験している暴力について、たぶん、男性と女性では、その対処の選択肢や優先順位が違うように感じる。少なくとも、日本では、そういって間違いない。DVの被害者となる多くの女性たちは、実は、男性以上に日常的に殺傷力のある道具――つまり台所にある包丁や刃物などだが――の使用には長けている。DVの加害者を殺すことで問題を「解決」することは可能だということは誰でもわかることだ。しかし、実際にそうした手段を選択する人はごくわずかだ。多くの被害者は、別の闘い方を選択する。
DVの被害者を支援する活動家たちも、加害者を殺すことが問題の解決になるとは主張しない。むしろ、暴力に対して暴力で対処するのではなく、被害者のために避難場所を用意し、加害者が接触しないような防御策をとり、法的手段を駆使し、同時に、加害者の更生への道を探るのではないだろうか。こうした活動は、DVを引き起す社会的な背景にも目を向けることになる。家父長制的家族制度や資本主義の市場経済がもたらす性差別主義のなかに、暴力によって支配を貫徹させる不合理な欲望を再生産する社会的な構造がある。問題は、暴力による報復や復習では解決できないのだ。暴力をもたらす構造からの解放という目的は、暴力という手段によって実現しえない。人びと、とりわけ男性の意識や価値観を変えるための挑戦が必須になる。こうした身近な暴力の話題を戦争という暴力の文脈のなかに置き換えて考えてみることが必要なのだ。
この暴力と正義の関係は、難しい哲学や政治学の議論ではない。私たちの日常的な解放への実践の積み重ねのなかで理解できることでもある。しかし、国家間の戦争になると、この日常の知恵がすっかり忘れさられてしまう。国家間であっても、DV同様、正義と暴力の間には何の因果関係もない。力が強い者、戦争に勝利した者が正義であることもあれば、不正義であることもある。(何が正義か、という問いを脇に置いて、の話だが)いずでれあっても、多くの犠牲者を生み出す。そしてまた、正義の目的のために戦いながら、戦場で実際に戦争犯罪を犯すのも普通の人びとなのだ。つまり目的が正義であることは手段もまた正義であることを保証するものではないし、正義の装いの下に隠された不正義は戦争ではあたりまえに見出される非人道的な出来事でもある。
暴力と社会変革の関係についての私の現在の基本的な考え方は、以下のようになる。武力を用いた解放は、マルクスの言う人類前史における解放の手段として、その意義を否定することはできない。しかし、将来においても、同様に、武力による解放が必須の手段になるべきではない。現代において暴力に特権的な地位を与えているのは、壮健な成人男性が社会の理想モデルになるような暗黙の価値観に基くものだ。女性、高齢者、子どもよりも、力のある男性の方が正義において優るという価値観だ。戦争の武器や装備がこの価値観を体現し、軍隊の組織原理を規定する。ジェンダーは社会的な概念だから、たとえ女性が兵士として参加しても、その構造が女性にマスキュリニティとファロセントリックな男性性に自己同一化することを強ることになる。
女性は、このモデルを側面から支える。戦場で闘う夫や息子を鼓舞し、その死を意味づけする役割を担い、銃後の兵站の労働力となり、国家に忠誠を誓う次世代を生むことを義務とされる。こうした家父長制的な構造は、性的マイノリティに不寛容でリプロダクティブライツを否定する。こうした暴力による支配に対抗するために、解放の主体もまた暴力に依存するという場合、この力のモデルを受け入れなければ、武力による勝利は見込めない、という悪循環に陥る。だから、正義と暴力の不合理な結び付きを意識的に断ち切る必要がある。
つまり、私たちが目指さなければならない解放の手段は、壮健な成人男性が社会の理想モデルになるようであってはならないのだ。だから、必然的に、この意味での男性性の象徴的な行為でもある暴力を拒否し、非暴力であるべきだ、ということになる。
6. 9条の限界と戦争放棄の新たなパラダイム
日本が憲法で戦争放棄を明記していていも、実際に戦争放棄を体現する国になっていない。その理由は、日本が真剣に過去の侵略戦争の責任と向き合ってこなかったからだということはこれまでも繰り返し指摘されてきた。私もそう思う。戦争責任を負うべき最大の戦犯は天皇ヒロヒトだ。しかし戦後、ヒロヒトは戦争責任を問われることなく、憲法によって日本国家の象徴になった。そして戦犯だった人達が戦後日本の支配の中枢を担い日米同盟の基礎を築いた。他方で、民衆の平和への指向は、被害者意識に基礎を置いたままだった。日本の戦争における加害責任あるいは戦争犯罪は、平和運動の中核的な基盤をなしてはこなかったのではないか。
戦後日本の平和運動を支えてきた理念にはいくつかの特徴がある。第一に、憲法が明記している戦争放棄条項を根拠に、自国の軍隊についても否定的な理解が共通の「理念」として確立してきた。第二に、この理念が広く共有されてきた背景には、日本が関った戦争への反省の特殊性がある。日本は植民地主義の侵略者だったが、戦後の平和を希求する最大公約数は、広島、長崎の原爆や空襲の被害であり、侵略地での日本軍の玉砕に象徴されるような自国兵士の悲劇、植民地での日本からの開拓移民の悲惨な経験など、戦争被害体験だ。だから日本の戦争責任を問う声が政治を動かすほどの影響力をもったことはほとんどない。戦争の最高責任者であった天皇ヒロヒトは、民間の取り組みである女性国際戦犯法廷によって有罪判決が出されているが、一度も公的に戦争責任を問われず、戦犯としても裁かれていない。ヒロヒトは、戦後も国家の象徴として君臨し、戦犯たちが戦後政治の中心を担ってきた。自国の侵略や軍国主義への抑止となる平和主義は、自国の加害責任、侵略の責任に基く必要があるが、戦後日本の平和運動ではこの点が決定的に脆弱だった。とはいえ平和運動は、ここ半世紀近く、日本の戦争責任に注目するという変化を次第にみせてきた。これに対して、政府も右翼、保守派も日本の戦争犯罪、戦争責任を認めない態度は一貫している。
上の背景を踏まえて、9条の限界について四つの理由を述べたい。ここでの限界は、9条そのものではなく、なぜ戦争放棄を実現できないのかについて、戦後日本の統治機構全体の文脈を視野に入れての理由である。
ひとつは、死刑制度の存在だ。政府も世論も死刑存置が圧倒的な多数派を構成している。死刑は、国家が殺人によって正義を実現するという理不尽な法制度だ。世論の死刑への支持は圧倒的多数を占める。日本では、民衆のレベルで、暴力、報復によって「正義」を実現することが容認されている。3死刑制度とは、自国民を矯正できず、報復し抹殺することで秩序を維持しようとする制度でもある。このような国に、どうして戦争放棄など可能だろうか。
では、死刑廃止国であっても軍が存在するのは何故なのか。それは、殺害の対象が「他者」だからだ。では、殺してもいい「他者」とは、いったい誰にとっての他者なのか。それは、私にとっての他者でない。国家にとっての他者だ。私は、「他者」であれば命を奪うことが許されるという考え方に反対だ。ここには、西欧近代国家の普遍的な人権概念と近代国家が生み出す「他者」との間にある克服しがたい矛盾が存在する。
もうひとつは、日本のジェンダーギャップ指数が極端に低いということだ。世界経済フォーラムの統計では116位だ。経済力との関係を考慮すると異常な低さだと言わざるをえない。 日本では、同性婚もLGBTQ+の権利も法制度として認められていない。憲法では個人としての尊重を明記しているが、戸籍制度という世界に類をみない家族を中心とする公的な制度が存在しており、実際には、個人を超越する男性を中心とする家父長制意識を制度が支えている。こうした感情を女性もまた内面化するので、ここでの問題は、単純な生物学的な「性別」の問題ではない。暴力において優位に立つことができる男性性への同調の構造が問題なのだ。前述したように、こうした環境が暴力を正当化する枠組をなしてきた。
第三に、これも前述したように、日本はほとんど難民を受け入れていない、ということだ。法務省のデータによれば、2021年の難民認定数はたったの74人にすぎない。難民認定申請者は2413人だった。この数字は異常というしかない。また、人口1億4000万人のうち在留外国人は約280万人で西欧諸国より圧倒的に少ない。文化的多様性に欠け、他者への排除意識が作用しやすい環境にある。こうした環境は、自国の文化や伝統へのロマン主義的な傾倒を生みやすく、このことが戦争を美化し賛美する文化をもたらす。合理的な他者への評価よりも、感情的な美意識が排除と差別を生む。つまり、日本の平和とは、自民族中心主義がもたらす美学に支えられているので、この日本文化への侵犯への敵意が醸成されやすい。19世紀のヨーロッパのロマン主義も日本浪漫派も戦争の美学によって暴力を賛美した。
最後に、その上で、歴史の教訓として、近代国民国家が戦争なしで国際関係を構築することができたかどうかを問うことが必要だ。世界中に200近くの国家があり、この国家がお互いに、最高法規としての憲法を持ち、互いにその優位を競う世界体制と、家父長制的な暴力と温情主義の弁証法が支配するこの世界のどこに平和の可能性があるのだろうか。現実主義者は、この現実を肯定して、武力による解決を肯定する。上述したように、この解決方法に合理性はない。だから、私は未だ実現しえていない世界を夢想することになる。私は、ある種の理想主義を選択する以外にないと思っている。憲法に戦争放棄、あるいは戦争を拒否する権利を明記することは、このような国民国家の宿命的な暴力的性格を自己批判することでもある。そして、日本は、他者との関係構築において――つまり外交だが――武力を後ろ盾とした交渉とは全く異なる外交パラダイムを持つ必要がある。これは、国民国家の自己否定を内包するラディカルな立場だ。左翼がこうした立場をとることによって、暴力という手段によらない解放の可能性を模索することが、人類の前史に終止符を打つための重要な課題になる。
7. 二人のファノン――締め括りのためのひとつの重要な宿題として
このやや長いエッセイを締め括るにあたり、暴力と解放闘争の議論では避けて通れないファノンの『地に呪われたる者』を取り上げておきたい。解放の暴力を肯定する議論として、その第1章「暴力」はよく言及されるテキストだ。しかし、第1章と対をなす最終章、第5章「植民地戦争と精神障害」にもっと多くの注意を払うべきだと思っている。ファノンは、人種主義的な従来の精神医学を厳しく批判した。この指摘を可能にしたのは、植民地解放の闘いがあったからだ。第5章は、植民地精神医学の分野では、人種主義的な精神医学批判として高く評価されている。4 ファノンは次のように述べている。
「アルジェリア人の犯罪性、その衝動性、その殺人の激しさは、したがって神経系組織の結果でも、性格的特異性の結果でもなく、植民地状況の所産である。アルジェリアの戦士たちがこの問題を論議し、植民地主義によって彼らのうちに植えつけられた信条を怖れることなく疑問に付したこと、各人が他人の衝立であり、現実には各人が他人に飛びかかることによって自殺しているのだという事実を理解したこと――これは革命的意識において本源的重要性を持つべきことであった。」
「戦う原住民の目標は、支配の終焉をひきおこすことだ。しかし、彼はまた同様に、抑圧によってその肉体のうちにたたきこまれたあらゆる真実に反することを一掃すべく心を配らねなならない」(鈴木道彦、浦野衣子訳、みすず書房、p.179。ただし旧版による)
第5章に関して私が重要だと思うのは、こうした抽象的な議論の前提になっている具体的な症例についての詳細な記述だ。後に心的外傷性ストレス(PTSD)と呼ばれることになる戦争がもたらす深刻な被害は、解放戦争においても例外ではなかった。解放戦争そのものは、精神的な外傷を生み出すことがあっても、これを克服することはできない。だから症例と総括的な文章との間には、埋めなければならない大きな溝があると思う。そのことにファノンは気づいていたと思うが、残念ながら彼は1961年に他界した。アルジェリアの独立は翌年1962年だ。彼は、戦後を経験していない。
20世紀の戦争を遂行してきた主要な国々は、心的外傷の課題を残酷な戦争に耐えうる兵士のパーソナリティの構築と、そのための精神医学の動員として展開してきた。5これに対して解放戦争の側がオルタナティブを提起できているとは思えない。ファノンは、戦争で心を病んだ人達の回復を解放された社会に委ねているが、同時に、暴力の問題について「すでに解放されたマグレブ諸国でも、解放闘争中に指摘されたこの同じ現象が持続し、独立とともにいっそう明確になっているのだ」(前掲、p.178)という示唆的な文章を残している。
この第5章と暴力という手段によって解放を実現することを論じた第1章の間には、十分な整合性があるとはいえない。特に、第5章における個別の症例を論じている精神科医としてのファノンと、この症例を総括して植民地解放運動全体の文脈のなかに位置づけようとする解放戦争の闘士としてのファノンの間には未解決の溝があると思う。
戦争におけるPTSDの問題をDVにおけるPTSDとひつながりのものとして把えたジュディス・ハーマンの仕事に私は多くのことを学んだ。(参照文献をごらんください)また、最近沖縄の地上戦がもたらしたPTSDに注目したいくつかの著作によっても示唆を受けた。6専守防衛であっても戦争となれば、たとえ生き延びたとしても、このPTSDの問題は一生を通じて残ることになる。だから、PTSDを、解放実現のための止むを得ない犠牲と考えるべきではないと思う。殺すこと、殺されることだけではなく、戦争や暴力にはあってはならない多くの「止むを得ない」犠牲があり、これを代償としてなし遂げられる「解放」に私は未来を託す覚悟はない。これもまた、武器をとらない、という私の選択の重要な理由になっている。
8. 参照文献
ここに紹介する3冊の本は、この原稿を書くときに常に念頭にあった本だ。いずれも刊行年は古いが、今読むべき本だと思う。いずれもまだ書店で入手できる。
●トルストイ『トルストイの日露戦争論』平民社訳、1904年。
1904年6月27日のロンドンタイムズに掲載された長文のエッセイBethink Yourselves!を幸徳秋水らが翻訳した。日露戦争(1904-1905)が勃発すると、戦争に反対する幸徳秋水などの社会主義者が「平民社」を設立。平民社は、トルストイのエッセイ “Bethink Yourselves!”を翻訳し、出版した。トルストイはこのエッセイでロシア皇帝と天皇を同時に批判し、断固として戦争に反対した。幸徳は解説の中で、戦争のない社会としての社会主義の主張がないことを批判しつつもトルストイの主張をほぼ全面的に支持している。ウクライナで戦争が起きている今、非戦論の文献として最も優れたもののひとつと思う。 英語原文は下記で読める。(マルクス主義のアーカイブサイトにトルストイの文章が掲載されているのも珍しいかもしれない) https://www.marxists.org/archive/tolstoy/1904/bethink-yourselves.html 平民社訳は、国会図書館のオンラインで閲覧が可能だが、『現代文 トルストイの日露戦争論』として国書刊行会が2011年に出版しており、入手できる。
●ジュディス・ルイス・ハーマン、『心的外傷と回復』、中井久夫訳、みすず書房。1999年。
ハーマンはその序文で次のように書いている。(原書から小倉の訳)
『心的外傷と回復』は、性的暴力や家庭内暴力の被害者を対象とした20年にわたる研究と臨床の成果である。 トラウマと回復』は、性的暴力や家庭内暴力の被害者を対象とした20年にわたる研究と臨床の成果を示すものである。また、この本は、他の多くのトラウマを抱えた人たちとの経験の積み重ねを反映している。 また、他の多くのトラウマを抱えた人々、特に戦闘に参加した退役軍人や政治的恐怖の犠牲者に対する経験も反映されている。 政治的恐怖の被害者である。本書は、公的な世界と私的な世界、個人と個人の間のつながりを回復するための本である。 公私の間、個人と地域社会の間、男性と女性の間のつながりを取り戻すための本だ。
●デイヴィッド・デリンジャー、『「アメリカ」が知らないアメリカ―反戦・非暴力のわが回想』吉川勇一訳、藤原書店、1997年
武装抵抗の支持者の中には、非暴力主義者を臆病者と揶揄する人もいる。本書は、非暴力不服従としての平和主義の実践は議会主義や日和見主義とは全く異なる生き方であることをよく示した自伝。第二次世界大戦中、デリンジャーは、ファシズムやナチズムを完全に否定しながらも、徴兵を拒否し、ドイツ爆撃に反対し、そのために投獄された。第二次世界大戦後は、2004年に亡くなるまで、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争と、すべての戦争に反対し、何度も投獄を繰り返し経験した。日本では小田実らのベ平連の運動との交流があり、小田実との共著『「人間の国」へ―日米・市民の対話』ギブソン松井佳子訳、藤原書店、1999年がある。
Footnotes:
「自衞をする場合に、外交の力によつて自衞することもありましようし、或いは條約の力によつて自衞することもありましようし、その方式はいろいろありましようが、とにかく日本を守るということは、武力による自衞権を行使しないということははつきり憲法の條章によつて、この点は明らかである 」吉田茂 第7回国会 参議院 予算委員会 第18号 1950年3月22日
https://rageagainstwar.com/ この集会にはピンク・フロイドのロジャー・ウォーターやクリス・ヘッジスなども発言者として登場した。
「死刑制度に関して、「死刑は廃止すべきである」、「死刑もやむを得ない」という意見があるが、どちらの意見に賛成か聞いたところ、「死刑は廃止すべきである」と答えた者の割合が9.0%、「死刑もやむを得ない」と答えた者の割合が80.8%となっている。なお、「わからない・一概に言えない」と答えた者の割合が10.2%となっている。 都市規模別に見ると、「死刑もやむを得ない」と答えた者の割合は中都市で高くなっている。 性別に見ると、「死刑もやむを得ない」と答えた者の割合は男性で高くなっている。 年齢別に見ると、「死刑もやむを得ない」と答えた者の割合は30歳代で高くなっている。」2019年、基本的法制度に関する世論調査、https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-houseido/index.html
角川雅樹「Frantz Fanonと 植民 地心理〜マルチニークとメキシコの事例から〜」ラテンアメ リカ研究年報 No.11(1991年);「フランス植民地の精神医学」akihitosuzuki’s diary、https://akihitosuzuki.hatenadiary.jp/entry/2008/12/01/104634 ;Keller, Richard C., “Pinel in the Maghreb: Liberation, Confinement, and Psychiatric Reform in French North Africa”, Bulletin of the History of Medicine, 79(2005), 459-499 ;UNCONSCIOUS DOMINIONS, Edited by warwick anderson, deborah jenson, and richard c. keller, Duke University Press, 2011.
戦争による心的外傷についての最初のまとまった研究は、フロイトらの研究『戦争神経症の精神分析にむけて』である。フロイトの「緒言」が『フロイト全集』(岩波書店)第16巻に収録されている。フロイト後の経緯については、アラン・ヤング『PTSDと医療人類学』、中井久夫他訳、みすず書房、参照。
蟻塚亮二『沖縄戦と心の傷 トラウマ診療の現場から』、大月書店、2014;沖縄戦・精神保健研究会『戦争と心』、沖縄タイムス社、2017、参照。
Author: toshi
Created: 2023-02-27 月 22:49