議会も司法も崩壊する―「デジタル庁」構想の本質とは
菅政権になり、デジタル庁の設置など政府のネット政策が急展開の様相をみせている。また、新型コロナの接触確認アプリの動向は、世界規模で、従来のプライバシーの権利との関連で大きな議論をまきおこしている。
2020年9月16日菅は首相記者会見でデジタル庁新設に言及し、9月23日デジタル改革関係閣僚会議では「デジタル庁は、強力な司令塔機能を有し、官民を問わず能力の高い人材が集まり、社会全体のデジタル化をリードする強力な組織とする必要があります。」と述べ、年末までに基本方針を策定し通常国会に必要な法案提出するとともに、IT基本法の抜本改正も行うとした。
10月26日所信表明演説では、デジタル庁を中心に、中央省庁だけでなく「自治体の縦割りを打破」することに踏みこみ、マイナンバーカードも二年半で全国民配付という目標を提示し、来年三月から保険証とマイナンバーカードの一体化を開始、運転免許証のデジタル化の導入も宣言した。
注目すべきなのは、情報インフラの統合を通じて、地方自治を中央省庁に統合し、省庁の情報インフラの統合によって、官邸の統制を一気呵成にアップグレードすること、そのために民間のITの技術力を大幅に導入するとしたことだ。分権的な行政権力がかろうじて残されてきた地方自治を解体することによって、21世紀型の官邸によって統制される内務省体制の権力構造への転換が浮上してきているといっていい。政権と国内外の民間巨大ITビジネス(これが現代資本主義の支配的な産業であり政治的権力の後ろ盾となりうるものだ)の利害が一致しているところが現政権の強みといえる。
しかし、システムの省庁統合は、コンピュータ回線を繋げば実現できるようなものではない。大規模なシステム統合は民間でも急速に進みつつある分野で、一般にDX(デジタル・トランスフォーメーション)と呼ばれているが、その実現は至難の技で、簡単ではない。数年以上の時間がかかることもマレではなく、システムのトラブルは避けられず、行政保有の個人情報を様々なリスクに晒し、とりかえしのつかない被害が起ることが十分に考えられる。
しかも、関連する法改正も一筋縄ではいかないだろう。基本法について菅はIT基本法だけしか言及していないが、知的財産基本法(2002)、サイバーセキュリティ基本法(2014)、官民データ活用推進基本法(2016)があり、下位の法律も膨大な数になる。法制度を調整して実際にデジタル庁を新設するために必要な手続きが必要で、省庁DXの技術的な難問にに加えて問題はより複雑になる。こうした制度の改変のどさくさにまぎれて、必ず私たちの権利を抑圧するような改悪が忍び込むことはほぼ間違いない。最大の注意を払わなければならないと思う。
デジタル庁構想は、安倍政権のSociety5.0の具体化の取り組みとみることができる。Society5.0は、人工知能、次世代通信網5G、そしてビッグデータの活用による未来社会構想だが、5月に成立したスーパーシティ法(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律)で法的な裏付けが与えられた。この嘘っぽい将来構造を資本が利用しようとするとき、この欺瞞的な未来社会が実現可能かもしれないと大衆に誤認させるきっかけが与えられることが考えられる。戦前の大東亜共栄圏から最近のバブル経済、小泉改革、そしてアベノミクスも、政権と資本によって煽られた「経済的な豊かさ」の幻想によって資本主義の実態が巧妙に隠蔽されてきた。同じことがSociety5.0やスーパーシティでも繰り返されるのは目に見えている。
政権が絵空事のようにして描くネット社会は、過去から現在に至るまである共通した特徴がある。それは、こうした社会の住人たちの政治的な権利、あるいは民主主義的な意思決定、権力に対して異論を唱える表現の自由や政治的な自由の権利がどのように保障されるのか、ということは一切言及されないという点だ。この未来社会に済む住人はみな既存の政治的な権力を肯定し、自らの私的な幸福を充足することにしか関心を持たないような人間が前提されている。こうした未来社会では、異議を唱える者は、この社会から排除されるか抹殺されることが暗黙のうちに含意されている。権力の本質からすれば、敵対者を啓蒙によって同意を形成することと、この同意からも逸脱する者たちを排除する力を持つこと、この二つのバランスの上に権力としての正統性を再生産しようとする。テクノロジーはこうした権力を支える。コンピュータによる監視の技術は、私生活の利便性、教育による啓蒙、より強固な労働と私生活への監視的介入、そして逸脱者のあぶり出しと懲罰、これらのいずれにも作用する。
従って、コンピュータによる高度なデータ処理、5Gによる家電などモノのインターネットの普及、そしてAIによる将来予測がデジタル庁の基盤になるとすると、現在の議会制民主主義も司法制度もほとんど実質的な権力分立による行政権力への牽制を果せなくなる。それだけではなく、立法と司法が依存する憲法を含む法の支配そのものも有効性が削がれることになる。米国の憲法学者、ローレンス・レッシグはコンピュータのプログラム・コードが法を出し抜くようになると指摘したが、コンピュータが行政権力の中枢を支配する社会では、議員も裁判所も理解しえないコードが法を超越するようになるのは間違いないと思う。今でも、行政のコンピュータであれGoogleやAmazonが運用するビッグデータから捜査機関の盗聴装置やコロナの濃厚接触者追跡アプリや保健医療システムに至るまで、ほとんど全ての資本と国家のコンピュータはブラックボックスのなかにあり、私たちにはアクセスできない。こうしたコンピュータの解析能力を既存の権力者が独占し、投票行動の分析などに利用されることによって、選挙制度そのものが歪められる。選挙の匿名性は有名無実になりつつあり、商業広告の進歩と連動して有権者の投票行動を予測して投票を誘導する技術の進歩は目覚しい。こうした事態のなかで、議会制民主主義は、その理念通りには機能しなくなっている。にもかかわらず理念を現実と誤解すると、議会制民主主義や裁判制度に過剰な期待を寄せることになってしまう。こうなってしまうと権力の思う壺だと思う。
他方で、権力者が武器としているテクノロジーと同じ原理で機能するテクノロジーが私たちの手にもある。このテクロジーが個人情報を収集する権力の手先になるのか、それとも逆に権力と闘うコミュニケーションの武器になるのかは、実は私たちが御仕着せで便利に使ってきたコンピュータの罠を回避するような手だてを講じられるかどうかにかかっている。この手だての第一歩は、匿名性の確保と権力に監視されないコミュニケーション環境の防衛(中心をなすのが権力の介入を許さない暗号化だ)にあると思う。ビッグデータと監視を阻止する手段が私たちの手のなかにもある。世界中の活動家たちが、とりわけ弾圧の厳しい国・地域では匿名性と集団的なプライバシーの防衛は必須だ。こうしたテクノロジーのオルタナティブを私たちが学ぶこともまた運動のライフスタイルを変える一歩になるし、既存の民主主義とは異なる民衆の合意形成の可能性に道を開くことにもなると思う。
初出:人民新聞2020年12月5日(リンクなどを追加しました)
 Facebook、Twitter、YouTubeへの公開書簡。中東・北アフリカの批判的な声を黙らせるのはやめなさい。
Facebook、Twitter、YouTubeへの公開書簡。中東・北アフリカの批判的な声を黙らせるのはやめなさい。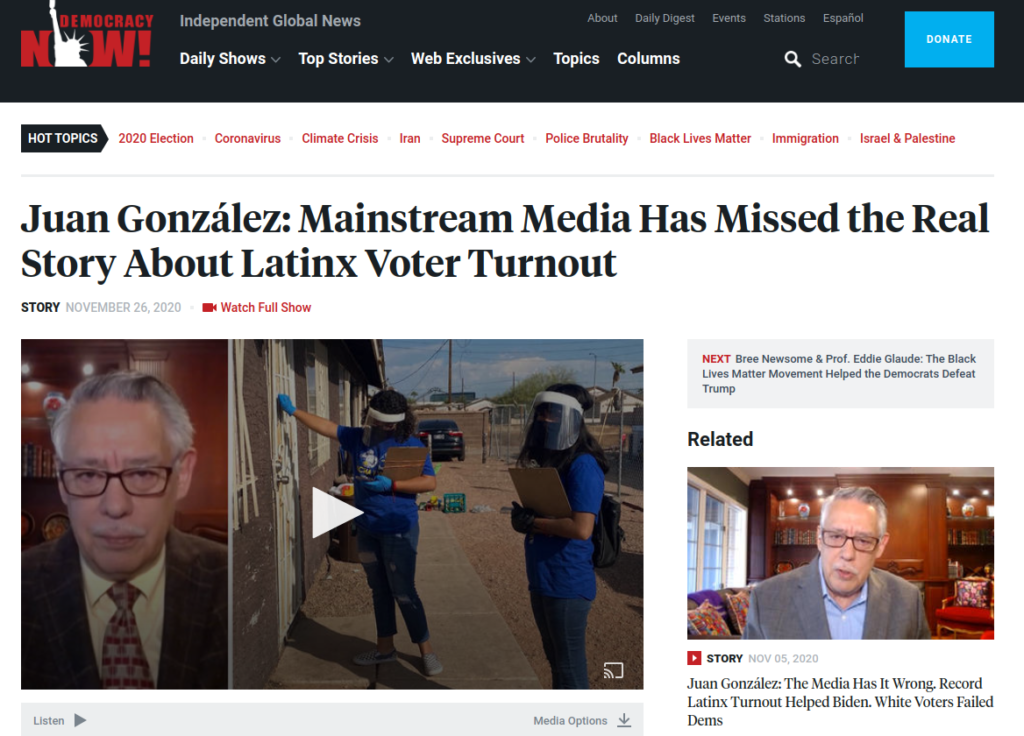 Juan Gonzalez
Juan Gonzalez Between Electoral Politics and Civil War
Between Electoral Politics and Civil War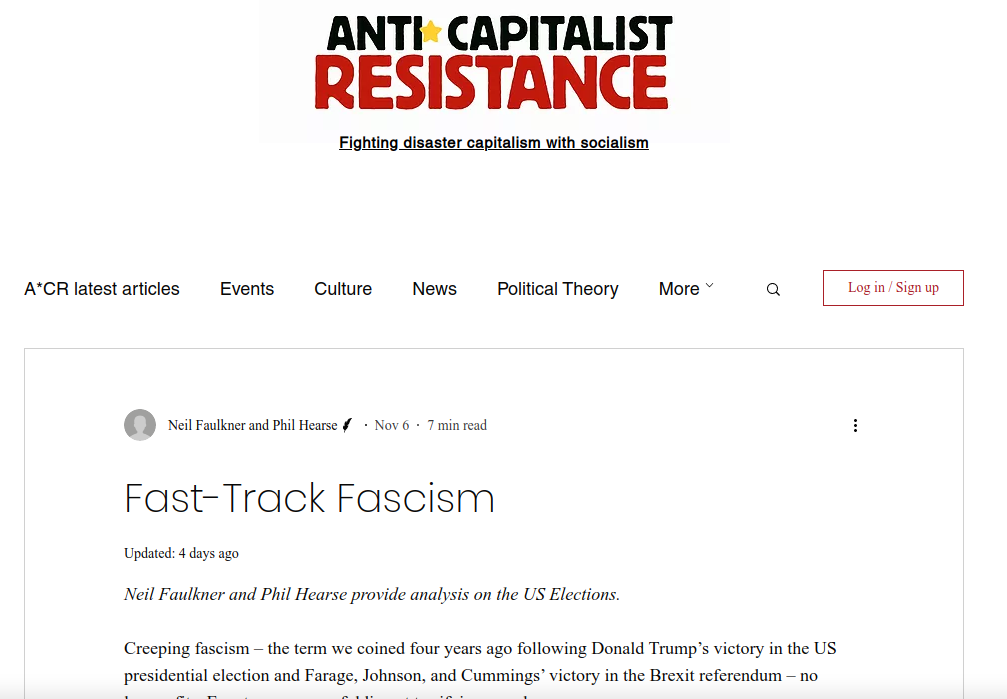 以下は、Anti Capitalism Resistanceのサイトに掲載されたPhil Hearse「選挙後の忍びよるファシズム」という記事の紹介である。
以下は、Anti Capitalism Resistanceのサイトに掲載されたPhil Hearse「選挙後の忍びよるファシズム」という記事の紹介である。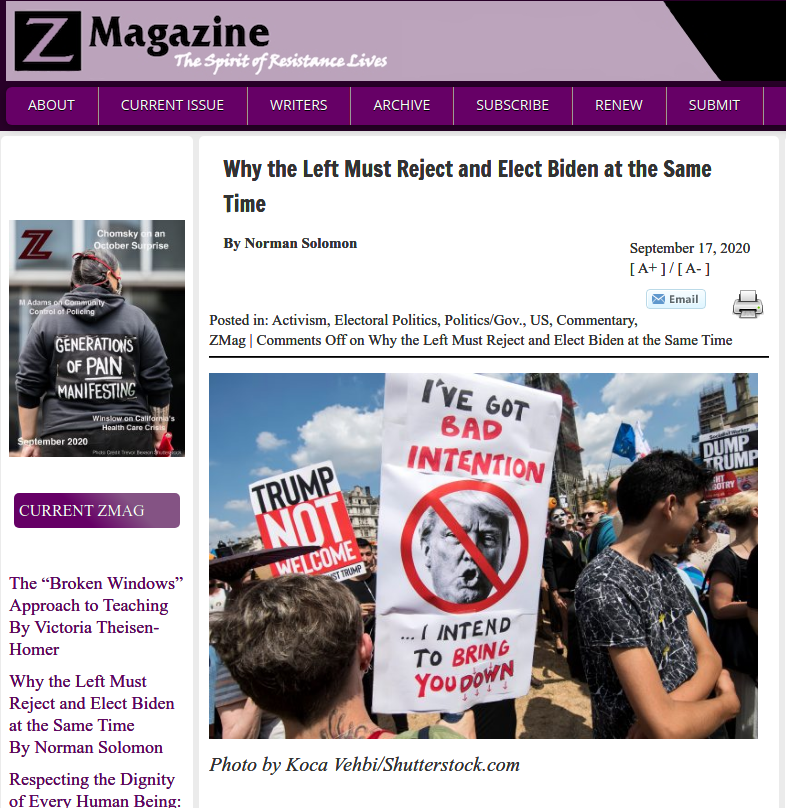 選挙運動でサンダースを支援してきた民主党左派とその支持者たちにとってバイデンのお評判は悪かった。(だからバイデンではなくサンダースを支援したわけだが)RootsAction.orgの代表、ノーマン・ソロモンは、サンダースの支持者たちが、バイデンが民主党の正式な大統領候補になった後に、バイデンに投票するための作戦を意識的に展開してきた。
選挙運動でサンダースを支援してきた民主党左派とその支持者たちにとってバイデンのお評判は悪かった。(だからバイデンではなくサンダースを支援したわけだが)RootsAction.orgの代表、ノーマン・ソロモンは、サンダースの支持者たちが、バイデンが民主党の正式な大統領候補になった後に、バイデンに投票するための作戦を意識的に展開してきた。