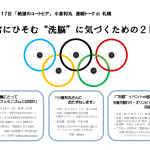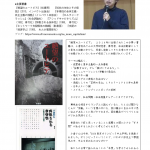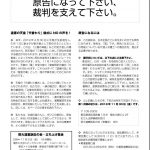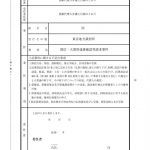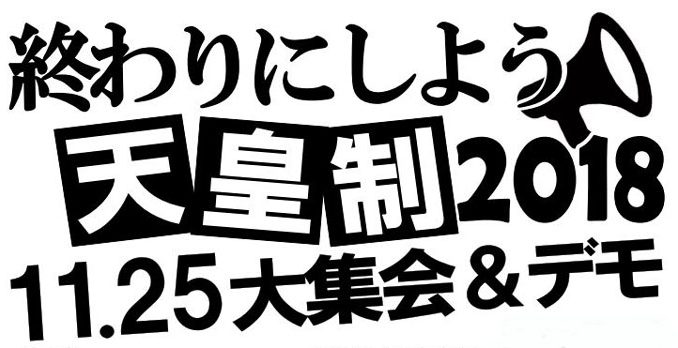
終わりにしよう天皇制2018 11・25大集会&デモ → download
講演:栗原康さん(アナキズム研究)
芝居:野戦の月(予定)
コント、歌、アピールなど予定!
日時:2018年11月25日(日)午後1時15分開場/1時30分開始 ※集会後デモ
会場:千駄ヶ谷区民会館2階集会室
主催:終わりにしよう天皇制!「代替り」に反対するネットワーク
天皇の自己申告で始まった「代替り」も、いよいよ佳境に入りつつある。2019年4月30日明仁退位、翌5月1日メーデーに堂々の新天皇徳仁即位。秋には即位礼、大嘗祭。奉祝賛美の雨あられ、「お人柄」報道の大洪水。
腐っている。もう全面的に腐っている。忖度とおべんちゃらの腐敗臭があたりに充満している。もう耐え難い。耐え難きは耐えられない!
だから私たちは、「終わりにしよう天皇制!『代替り』反対ネットワーク」を結成し、来年11月までの集中的な闘いを挑む。
昨年大好評だった「終わりにしよう天皇制大集会デモ」を11月25日に開催し、これをネットワークの活動のスタートとしたい。
天皇制に反対する皆さん、「代替り」プロセスに異議ある皆さん、よく分からんけど変だと思う皆さん!来たれ11・25集会デモに!
超総力結集でよろしくお願いします!