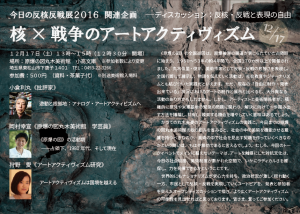オリンピック否定論の根底に置くべき視点は、そもそも近代社会が「スポーツ」というカテゴリーによって構築した人間の身体のありようそのものが、資 本主義における身体搾取の現われであるというところに定められるべきだ、ということだ。資本主義的な搾取が否定されなければならないという問題の一つの系 論として、スポーツに表出される身体のありようへの批判が位置付けられるべきなのである。これは容易に理解されないことかもしれないが、私たちが、スポー ツというスペクタクルによって動員される自己の同調感情やある種の高揚した感情の根底にあるのは、近代社会が人びとの身体の根源に埋め込んだ身体の理想と 深く関ることであり、この理想の罠といかに闘うかが課題だといっていい。
近代社会においてスポーツは「娯楽」というカテゴリーのなかで、圧倒的な大多数を「観衆」の位置に置きながら、ごく一部の者たちがこの「観衆」の前 で演じる身体表現として成り立つものだ。これは、音楽が、演奏者と聴衆に、美術が美術家と鑑賞者に、文学や哲学などの学問が学者や作家と読者に分けられる ことによって成り立つ文化生産と消費の構造と同一のものといっていい。あるいは、近代西洋医学が、人びとの身体についての知識を奪い医者という特権的な専 門家を生み出したように、自己の身体性は、自己の統治の下にあるのではなく、これを様々な専門家に委ねることによって、生を支える根源的な力を奪われ、あ るいはこうした専門家に委ねることで支配と従属の関係に自ら身を委ねる。この構造そのものを土台として成り立つ身体性(肉体としての身体であれ、言語能力 であれ、非言語的な表現であれ)が同時に、資本主義社会が不可欠とする身体の見取り図あるいは規範的かつ理想的なモデルの提示でもあるということ、このこ とを踏まえるならば、こうした文化的な身体が生産する行為や「作品」がいかに感動的なものであったとしても、その感動を生起するわたしの感性そのものを疑 うことなくして、資本主義を深い懐疑の闇のなかに投げ入れることなどできようはずがない。
最大の困難は、こうした文化が生み出す感動や共感といった実感としては否定しようのない肯定的な感情を突き放し、ここに懐疑の楔を打ち込むという苦 痛な作業をあえて行わなければならないというところにある。感動を疑うこと、感動する自己の感情や心理がどのような社会的な条件に規定されて生成されるの かを冷静に突き止めることが必要なのだ。
近代スポーツ(近代以前には「スポーツ」と呼びうる身体の使用があったとは思えないが)の特徴は、身体をスピードと正確性によって評価する構造を基 本に据えているという点にある。これは、近代社会の労働する身体がスピードと正確性という価値判断によって構築されていることと無関係ではない。
より速く、より正確に、決められた時間内で結果を出すという枠組のなかで身体をめぐる競争(闘争)が組織されるのがスポーツの基本的な枠組である。 この枠組は、工業化社会を前提として成立した「資本」の行動原理が個々の人間の行動規範として内面化され、ある種の倫理となる。速度=効率性は資本の投資 —利潤の回転の基礎条件であり、正確性は機械化された職場で人間が機械の正確性に適応することを必須の身体的な条件とされ、市場を予測し売上げを確定させ ることが資本にとってのリスクとロスを最小化する手段となる。こうして古典的な文化や芸術の世界では、即興や一回性の表現は排除され、聴衆の前で、一定の ルールを前提とした繰返しを前提とした差異や特異性が争われるようになる。
近代化のなかで近代以前からある身体競技はその社会的な文脈も意味も変容し、そのスタイルを「伝統」として意味づけることによって、資本主義に固有 な身体の規範や文化的な価値があたかも普遍的なものであるかのように装われることになる。オリンピックが古代ギリシアにその起源をもつという神話はその典 型だろう。しかし、現代においては、むしろオリンピックが古代ギリシアにしかその起源を持つことができていないということが逆にオリンピックの世界性に疑 問を付すことになっている。非西欧世界の多様な文化が、ギリシアに起源をもつ身体の普遍的な「力」の誇示を競うゲームと接触する事態と、非西欧世界が近代 化=工業化の過程へと統合される事態との間にある相似形には根拠があるのだ。日本が1964年の東京オリンピックに過剰な意味を与えたように、北京オリン ピックもまた中国の資本主義化を象徴したものであったし、そしてまた今年のブラジル、リオのオリンピックもまたBRICSの一角を占めてラテンアメリカの 新興国としての国威発揚を担うものとして企図された。オリンピックはこの意味で、西洋中心主義の身体をめぐる価値を国民国家として総括するという近代世界 が前提としてきた世界システムの枠組の一翼を担っている。しかし、西洋の価値観が世界を支配することを正当化する露骨な西洋中心主義であることに皆が気づ かざるをえないのが現代という時代ではないか。イスラーム復興運動は、こうした西洋が僭称する普遍的な文化的価値に対してみずからのアイデンティティを対 置する。こうした事態が今日ほど広汎に、しかも政治的な摩擦や緊張を伴って登場した時代はない。たぶん、多文化主義というポストモダンな多様性の統合様式 の副作用として、世界中にある様々な「伝統的社会」のなかのある部分がイスラームほどには大きな影響力をもたないとはいえ、西洋中心主義のいかがわしさに 背を向けはじめると一方で、逆に自らのアイデンティティを放棄してでも西洋的な価値に統合されることを選択するポストモンダンな近代主義の部分も登場し、 その双方の摩擦がますますのっぴきならない状態へと陥るのがこの時代の危機の特徴になるのではないか。
オリンピックが可視化したいくつもの分断線がこの危機を端的に示している。健常者のスポーツと障害者のスポーツ、男性と女性、国家に帰属しえない人 びとの排除と「難民」チームによる包摂、そしてお定まりのサクセスストーリーがもたらす競技の勝敗の物語に暗示される社会的「敗者」への差別。スポーツが 持ち込む価値判断の基準は、健常者と障害者というカテゴリーを越える人間としての生をそれ自体として肯定することはできず、障害者は健常者と対等に競争で きないことを前提として二重基準を当然のようにして持ち出す。スポーツの速さや正確さという価値規範(労働の価値規範でもあるが)そのものが差別を構造化 しているということを疑うことができない。。同様のことは男性と女性についても言える。いずれの場合も、そのどちらともえいない境界の上に立つ多くの者達 がいるのだが、このボーダーの存在を強引にあちらとこちらに引き裂く。高齢者や子どもはもちろんこうしたスポーツの行為者の側には立ちえないものとして排 除される。スピードと正確性を基準とするスポーツは、こうして多くの差別と分断を内包させながら、排除された者達を「観衆」として位置付けて感情的な同一 化を生み出す仕掛けをもっている。この仕掛けの中心をなすのが、ナショナリズムだということになる。ナショナリズムの幻想がどのようにして近代社会で再生 産されるのかは別に議論すべきことだ。
スピードの優劣を百分の一秒のレベル争ったり、行為の優劣をポイント化して数量によって序列をつけるというスポーツの評価体系は、資本主義がもたら した数値化による競争と評価をそのまま持ち込んだものだ。これは、学校の成績から会社による査定まで、生活全般を覆う。数値化(成績であれ給料であれ) は、行為そのものの意味を問うことなく、意味を数値に還元することによって、行為の無意味さを隠蔽する。100メートルをいかに速く走るかにいったいどの ような意味があるのかとか、酷暑のなかを猛烈なスピードで40キロ以上も走りつづけることで何が得られうのか、といった行為の意味を問うことは、スポーツ においてはタブーに近い。しかし、意味の欠如は歴然としているのだが、だからこそ、一方で、薬物の使用による身体改造が常態化し、多方で、無意味なことに 文字通り命を賭ける人びとへに感動をもたらすという、よくよく考えてみればダークな世界がここにはある。ワーカホリックとなってドラッグや酒に依存しなが ら働き続け、あげくの果てに心身を病み、命を絶つことすらありうる労働世界の残酷さとスポーツの世界のそれとはやはり相似形だといわざるをえない。スポー ツの無意味さに多くの人びとが気づかないことと、多くに人びとが教育の成果をを成績(点数)で評価したり、労働の評価を報酬の多寡で評価することに疑問を 感じない日常感覚と密接に結びついている。この無意味さにもかかわらず、多くの人びとはこれらの行為に感情を動員し感動したりマゾヒスティックな快楽を感 じたりする。資本主義がどのようにしてこのような特異なアーソナリティを形成したのかを解明することは、資本主義と訣別するための重要な課題だ。
自然に依存する社会では、自然のリズムを変えることはできず、自然を完璧に予測して制御することもできなかった。こうしたアルカイックな社会に秒単 位の正確性とか、飽くなきスピードアップとかを競うような「競技」への関心は持ちえなかった。もちろんこうした社会には、この社会が与える固有の行為の 「意味」の体系があり、この「意味」の体系もまた、実は意味の喪失の表現でしかない、といことではあるのだ。「機械」の出現は、この前提を崩し、人間の理 想モデルは機械のようであることになった。つまり、より速く、より正確に、そして、反抗することなく指示に従うこと。近代のスポーツはこのような機械の時 代の人間を典型的に表象する仕掛けとなった。この近代的な身体をめぐる意味の喪失を過去や非近代的な社会によって回復しようとする試みに私は魅力を感じな い。意味と意味の喪失は表裏一体であって、この罠から抜け出るには、「意味」という問題の立て方それ自体を問題にいなければならない。つまり、言語や身体 の表現や、人と人、人と自然の関係そのものである。こうしたやっかいなテーマがオリンピックに象徴されるスポーツの問題の根源にあるということ、オリン ピックだけでなくスポーツを含む文化的な身体表現の社会的な構成そのものが資本主義の身体搾取を支えているということ、このことだけをここでは指摘するの が精一杯のところだ。
【参考文献】(思いつくままに)
渡辺裕 『聴衆の誕生』、春秋社。
アラン・コルバン『身体はどう変ってきたか——16世紀から現代まで』、小倉孝誠他訳、藤原書店。
小倉利丸『支配の「経済学」』、れんが書房新社。
小倉利丸『搾取される身体性』、青弓社。
ワロン『ワロン/身体・自我・社会』、浜田寿美男訳編、ミネルヴァ書房。
イヴァン・イリイチ『脱病院化の社会』、金子嗣郎訳、晶文社。
小笠原博毅・山本敦久編『反東京オリンピック』、航思社。
 空族の新作『
空族の新作『